
【令和6年能登半島地震・豪雨】支援活動レポート 11月7日~11日
【能登半島豪雨】支援活動レポート 11月7日
熱海の土石流災害時に地域でたちあがった「テンカラセン」のみなさんが活動に参加されました。
またカインズの皆さんも引き続き活動に参加、その後珠洲市で花の寄せ植えの活動を行っていかれました。

能登は朝晩めっきり寒くなり、一けた台の気温が続きます。
冬になれば雪で再び孤立する地域もでてきます。
あとわずかでその時期がやってきます。
それまでにみんなで力を合わせてできる限り進めていくことができればと思います。
重機現場からのレポートです。
<<<<<以下本文>>>>>
今回の現場は女性2人が住まれるお宅で、家裏の山が崖崩れを起こし、大量の土砂が家の裏庭を覆っています。
3日間にわたる重機活動となりました。

1日目はまず雑木撤去から始まり、木の伐採と草刈機を使った草刈りを家主さんと共に作業しました。
1時間半くらいで完了後、重機と不整地運搬車を使ってダンプに積載し、埋立場まで搬出する作業を繰り返します。その作業に3日要し、一日目は3台分、二日目は5台分×2、三日目は5台分と計18台となりました。

あとは社協ボランティアさんによる側溝啓開が残っておりますが、ひとまず本日で重機案件については活動終了となりました。
私は今回初めて不整地運搬車を運転し、狭い中でどのように操作した方がいいか、試行しながら活動しておりました。これからも精進したいと思います。 (たむ)
【能登半島豪雨】支援活動レポート 11月8日
しばらく20代の若者たちが4名でボランティアに参加してくれていました。
若者たちならではの明るさとパワーはあちこちで笑顔をうんでいました。
中でも初参加だった青年からレポートが届きました。
若者たちならではの明るさとパワーはあちこちで笑顔をうんでいました。
中でも初参加だった青年からレポートが届きました。
<<<<<以下本文>>>>>
今回初めて災害支援のボランティア活動に参加しました。
能登に到着して見た光景、それは今の僕にはとてつもなく刺激を与えました。
能登に到着して見た光景、それは今の僕にはとてつもなく刺激を与えました。

震災で家が崩れ、土砂災害で山は削れ、道路は崩れ落ち、流木で塞がれている状態でした。
この度のボランティアでは、豪雨災害により目の前でご家族を失われた方のお家で家財運搬や泥出し、高圧洗浄などの活動をさせてもらいました。
そこのお家のお父さんは、「あれ以来、ひたすら何かをしていないと気が済まない」そうおっしゃっていました。
この度のボランティアでは、豪雨災害により目の前でご家族を失われた方のお家で家財運搬や泥出し、高圧洗浄などの活動をさせてもらいました。
そこのお家のお父さんは、「あれ以来、ひたすら何かをしていないと気が済まない」そうおっしゃっていました。

当時のことを思うととてもじっとしていられないお気持ちだったのかと存じます。
それでも、現在は復旧に向けて前向きに取り組まれ、私たちが支援に行った際も「ありがとうございました」「ほんとに助かりました」そう言って頂き、ずっと一緒に活動をされていました。
それでも、現在は復旧に向けて前向きに取り組まれ、私たちが支援に行った際も「ありがとうございました」「ほんとに助かりました」そう言って頂き、ずっと一緒に活動をされていました。
少しでもお力添えができたのかな、と思うと同時に、その何倍ものパワーと元気を与えられました。
次の現場では、貸出していたお家を返却してもらい、「これからもずっとこのお家に住み続けたい」という方のお宅でした。
そこにもきっと、たくさんの思い出、大切な何かがあるのかなと感じました。
次の現場では、貸出していたお家を返却してもらい、「これからもずっとこのお家に住み続けたい」という方のお宅でした。
そこにもきっと、たくさんの思い出、大切な何かがあるのかなと感じました。

これからの僕にできることは、SNS等で情報を発信し、少しでも興味を持ってもらい災害支援携わってくれる人を増やす、そして自分自身が積極的に参加することだと思います。
少しでも興味がある方は連絡してください。
自分の意思で行って自分自身で見て、聞いて、感じて学ぶ。これが一番大事だと感じました。
少しでも興味がある方は連絡してください。
自分の意思で行って自分自身で見て、聞いて、感じて学ぶ。これが一番大事だと感じました。
今回のボランティアで出会えたOPEN JAPANの方々、ボランティアに一緒に参加した方々は、これからの僕にとって必ず素晴らしい影響を与えてくれる存在です。
これからも、能登だけではなく様々な被災地の復旧に向かって取り組んでくれている方がいることを忘れずに、そして何よりもテレビでは放送されなくなったとしてもSNSなどで自分自身が発信し続け、被災された地域を忘れないように生きていきたいと思います。
これからも、能登だけではなく様々な被災地の復旧に向かって取り組んでくれている方がいることを忘れずに、そして何よりもテレビでは放送されなくなったとしてもSNSなどで自分自身が発信し続け、被災された地域を忘れないように生きていきたいと思います。
今回のボランティアで一人の人間として、また1歩成長することが出来ました。能登の皆さん、ありがとうございました。(まひろ)
【能登半島豪雨】支援活動レポート 11月9~10日
週末、能登町災害ボランティアセンターにもたくさんの方たちが参加してくださいました。
ボランティアセンターのサポートも行いながらみなさんと能登町内のあちこちで活動しています。
ボランティアセンターのサポートも行いながらみなさんと能登町内のあちこちで活動しています。

「今日あたりでちょうど四十九日でな」いつもお手伝いに入っているお父さんがぽつりとおっしゃられました。
道路際にはいつもきれいにお花を供えておられます。
道路際にはいつもきれいにお花を供えておられます。
必要とされるできることを、集まる皆さんと一緒に行っていければと思います。
二級建築士でもあるよろずやの平ちゃんがレポートをくれました。
二級建築士でもあるよろずやの平ちゃんがレポートをくれました。
<<<<<以下本文>>>>>
平ちゃんです
今年の4月から初めて災害支援を始め、早7か月が過ぎ、色んな情景を見て、色んな人に出会い、色んな心に触れ合わせていただいています。
皆さんもご存知の通り、元日に地震災害を受け、少しずつ復興へと向かっていく矢先に豪雨災害に見舞われました。
今年の4月から初めて災害支援を始め、早7か月が過ぎ、色んな情景を見て、色んな人に出会い、色んな心に触れ合わせていただいています。
皆さんもご存知の通り、元日に地震災害を受け、少しずつ復興へと向かっていく矢先に豪雨災害に見舞われました。

本当にこれからだってときに。
建築家系で育ってきた僕にできるのは”つくること”です。
収納するところがないなら、棚を作ります。
戸が閉まらなくて寒い思いをしていれば、建具を調整して、住みやすい環境を作ります。
収納するところがないなら、棚を作ります。
戸が閉まらなくて寒い思いをしていれば、建具を調整して、住みやすい環境を作ります。

悲しい出来事があって、それでも家のことをやらないといけない状況なら、同情することはできなくても、明るい現場を作って一緒に手伝います。
今できることを
今できるときに
今できる場所で
今できることを
今できるときに
今できる場所で
【能登半島豪雨】支援活動レポート 11月11日
今日活動に入ったのは震災で自宅横の大きな蔵が被災されたお宅で、公費解体前に家財出しをする事がミッションだった。
立派な蔵から明治時代や大正時代の書籍や帳簿が出てくる。一見、古いボロボロの紙だけれど、これは久田和紙なのだそう。
立派な蔵から明治時代や大正時代の書籍や帳簿が出てくる。一見、古いボロボロの紙だけれど、これは久田和紙なのだそう。

このお宅界隈の久田(きゅうでん)という土地は
楮(こうぞ)がよく取れて和紙作りが盛んだったそうだ。住民さんとのやりとりでこういう話を聞かせていただく時間が私は好きだ。
楮(こうぞ)がよく取れて和紙作りが盛んだったそうだ。住民さんとのやりとりでこういう話を聞かせていただく時間が私は好きだ。
………………………………………………………………
家財出しの活動に入らせていただく時、いつもつくづく思うのは自分たちが運んでいるのはただの家財ではなく、私たちの知らない住民さんたちの
家族の歴史だったり思い出だという事だ。
家財出しの活動に入らせていただく時、いつもつくづく思うのは自分たちが運んでいるのはただの家財ではなく、私たちの知らない住民さんたちの
家族の歴史だったり思い出だという事だ。

どんなにこれはいらないんじゃないかな、と思っても必ず住民さんにいるかいらないか確認するようにしている。
そこで気持ちが揺らいでいるなら無理に手離させないし、住民さんの決断に捨てるも取っておくも
相談されない限り、決して口出しをしない。
本当にいらないものだけ手離していただく。
そこで気持ちが揺らいでいるなら無理に手離させないし、住民さんの決断に捨てるも取っておくも
相談されない限り、決して口出しをしない。
本当にいらないものだけ手離していただく。
………………………………………………………………
手離す、という事は自分の生活やコンディションがある程度安定していてこそできること。
いわゆる断捨離は手離していく過程で物への執着がなくなる事で心穏やかに過ごせる効果がある。
手離す、という事は自分の生活やコンディションがある程度安定していてこそできること。
いわゆる断捨離は手離していく過程で物への執着がなくなる事で心穏やかに過ごせる効果がある。
けれど被災地に暮らす住民さんたちは発災直後からあまりに沢山の事を手離し、諦め生活をされているのだ。
発災直後はとにかく「もういい」「全部いらない」「とって置ける場所もないから」と思い切って処分される方も多い。
それが、取っておこうかな、どうしようかなと
悩める状況になってきた事はある意味、生活環境や心のコンディションが回復されてきている証拠でもあると思う。
発災直後はとにかく「もういい」「全部いらない」「とって置ける場所もないから」と思い切って処分される方も多い。
それが、取っておこうかな、どうしようかなと
悩める状況になってきた事はある意味、生活環境や心のコンディションが回復されてきている証拠でもあると思う。
だからこそまずはいま本当に不要なものだけを搬送し、あとは時間と場所が許すなら取っておいて、ゆっくり吟味していいんですよとお声をかける。
手離す、という事は想像以上にエネルギーがいる事だとつくづく思う。
手離す、という事は想像以上にエネルギーがいる事だとつくづく思う。

一緒に活動に入らせていただいたみゆきさんが
そのお宅のお母さんに寄り添いながら仕分けをされている姿が印象的だった。
そのお宅のお母さんに寄り添いながら仕分けをされている姿が印象的だった。
………………………………………………………………
コーヒーブレイクの時、
ひょんな事から「猿鬼伝説」の話になった。
コーヒーブレイクの時、
ひょんな事から「猿鬼伝説」の話になった。
猿鬼伝説は柳田地区に伝わる伝説だそうで
この地域の地名の由来が語られている。
出てくる地名が知っている地名で嬉しくなった。
この地域の地名の由来が語られている。
出てくる地名が知っている地名で嬉しくなった。
そういえば現場に向かう道も場所も知っている場所が増えたなぁと思う。
能登に来始めた右も左もわからなかった3月には想像できなかったことだ。
能登に来て住民さんと一緒におしゃべりをしたり
話を伺ったりするうちに知ったこと学んだこともたくさんある。価値観も色々変わった。
能登に来始めた右も左もわからなかった3月には想像できなかったことだ。
能登に来て住民さんと一緒におしゃべりをしたり
話を伺ったりするうちに知ったこと学んだこともたくさんある。価値観も色々変わった。
支援の形は色々だし、ボランティア活動はできる人ができる時にできる事をが大事だと、私自身、身動きが取れなかった時はその言葉に救われてきた。
けれど現地に来て住民さんやボランティアの先輩方、仲間たちと話をしたり聴いてこそ分かることもまたたくさんあると思う。
けれど現地に来て住民さんやボランティアの先輩方、仲間たちと話をしたり聴いてこそ分かることもまたたくさんあると思う。
………………………………………………………………
現場はまだまだやる事がいっぱいで、雪が降る前に対応したい事もたくさんある。
そして何よりお正月まであと1ヶ月半。
現場はまだまだやる事がいっぱいで、雪が降る前に対応したい事もたくさんある。
そして何よりお正月まであと1ヶ月半。
きっと年が明けた時、住民さんもオープンジャパンの仲間たちをはじめ、能登に関わる多くの人が1年前の元旦の事を想うだろう。
けれどその時に住民さんたち皆さんが安心で安全で温かい場所で過ごしていてほしいし、震災に続き豪雨災害も起き、心折れそうな本当に大変な1年であったけれど、去年よりちょっとずつ良くなってるよねと、新しい1年を希望と共に迎えて欲しいなと願っている。
けれどその時に住民さんたち皆さんが安心で安全で温かい場所で過ごしていてほしいし、震災に続き豪雨災害も起き、心折れそうな本当に大変な1年であったけれど、去年よりちょっとずつ良くなってるよねと、新しい1年を希望と共に迎えて欲しいなと願っている。
そのために本当に微力ではあるけれど
能登にいられるこの時を大切に、明日も一生懸命活動しようと思う。 (まい)
能登にいられるこの時を大切に、明日も一生懸命活動しようと思う。 (まい)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








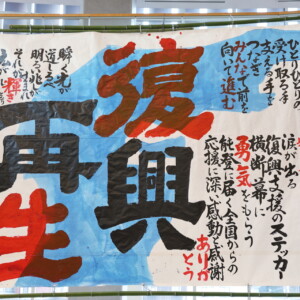


この記事へのコメントはありません。